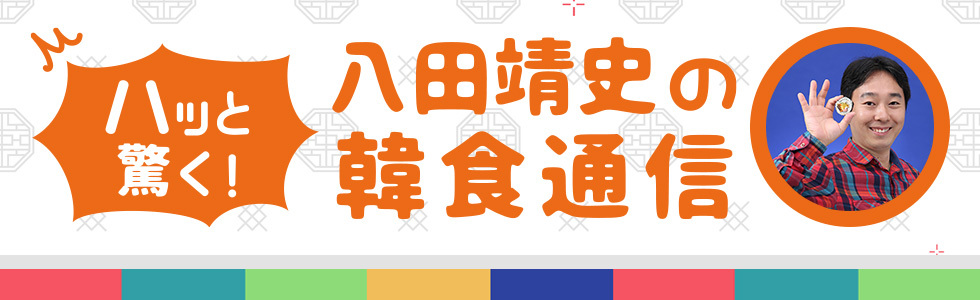韓国料理の世界では、なにかのきっかけでひとつの料理が流行り始めると、あちらでも、こちらでも素早く乗っかって、あっという間にその料理で埋め尽くされることが多々あります。本場の韓国はもちろん、日本の韓国料理店でも同じ現象が見られます。流行り始めからの推進力と拡散力がすごいので、トレンドと表現するよりも、なにやらお祭り騒ぎのような派手さがあります。
そんなブームが決して単発でなく、次から次へとやってくるのが、韓国料理の面白さと言えますね。近年の日本でいえば、2020年の「チキン(韓国チキン)」、2022年の「チュクミ(イイダコの炒め鍋)」、2024年の「ミナリサムギョプサル(セリと豚バラ肉の焼肉)」あたりが象徴的ですし、そこにスイーツや、パン、ストリートフードのトレンドも重なるので、日々なにか新しいものを追いかけている感覚があります。


(右)チュクミ(2022年)


(右)10円パン(2023年)
そんな視点から見ると、今後は「ナッコプセ(テナガダコと牛ホルモンとエビの炒め鍋)」が韓国料理の顔になっていくのではないかと思われます。もともと人気料理ではあるのですが、2025年に入って話題が増え、ずいぶんと勢いが目覚ましいです。
みなさん、ナッコプセの時代がやってきました。
■ 釜山名物ナッコプセとは?
そもそもナッコプセが広く知られるようになったのは韓国でも最近のことで、もともとは南部の釜山あたりで親しまれるローカルな料理でした。しかもこれ、看板料理というわけでもなく、オプションとして注文する派生メニューのひとつなんですね。
原形となるのは、釜山市東区の凡一洞を発祥とする、釜山式の「ナクチボックム(テナガダコの炒め鍋)」で、全国的にナクチボックムといえば炒め物を指すのですが、釜山では煮汁を多めにして鍋料理のように作るのを特徴とします。このアレンジが生まれたのは1960年代で、当時の凡一洞には「朝鮮紡績株式会社」という企業があり、そこの社員らが通ったことから現地では「朝紡ナクチ」の名前でも有名です。


(右)10番出口を出たすぐの貴金属通りがチョバンナクチの発祥地


(右)シメは煮汁にうどんを入れるのが現地流
そのチョバンナクチに、トッピングとして「コプチャン(牛の小腸)」や「セウ(エビ)」を追加する工夫が生まれたのが次なるステップで、ナクチ(ナッチ)、コプチャン、セウの頭文字を取ってナッコプセと呼ばれるようになります。3種類の食材それぞれの食感が異なるのに加え、お互いの旨味が重なり合って相乗効果でより美味しくなることから定番の組み合わせとして根付きました。
釜山の専門店に行くとナッコプセだけでなく、コプチャンだけを追加した「ナッコプ」や、エビだけを追加した「ナクセ(ナッセ)」といったメニューもあるのですが、よほどどちらかの食材が苦手でなければ、たいていは両方を追加するので、自然とナッコプセがいちばん有名になったようです。
こうして釜山で生まれたナッコプセが、全国区になるのは2010年代後半。
釜山の有名店がソウルへ進出したり、グルメ番組で取り上げられたりして徐々に知名度を高めていきます。日本で知られるようになったのは、2019年末にドラマ『孤独のグルメ』で取り上げられたのが大きかったですね。日本のみならず韓国でも大人気の作品ですが、しばしば韓国編があり「2019年大晦日スペシャル」にナッコプセが登場して話題になりました。
■ 日本における黎明期
このあたりが日本での黎明期となるのですが、ブームよりも早くナッコプセを提供していた店として東京・新大久保(歌舞伎町)の「ワンシンリ」があります。当時、看板を見つけてSNSに報告したところ、けっこうな反響があって、ナッコプセってこんなに人気の料理だったのかと驚いたのをよく覚えています。
今回改めて「ワンシンリ」で話を聞いたところ、初めてメニューに載せたのは2018年とのこと。もともとホルモン系の料理を得意としていましたが、釜山出身の友人から地元の料理としてナッコプセを教えてもらったのをきっかけとして、半年かけてタレの開発をしメニュー化したのだそうです。
「当時は誰もナッコプセなんて知らなかったですよ。でも、ウチは美味しい生のコプチャンがありましたからね。初めて食べる人もこれは美味しいとリピーターになって、いまでは看板メニューになりました。」
そもそも店名の「ワンシンリ(往十里)」はコプチャンで有名なソウルの地名。美味しいコプチャンに魚介を足せば、それはさらに美味しくなりますよね。






(右)ナッコプセの看板(2019年1月に興奮しながら撮影)
その後、日本では『孤独のグルメ』の効果もあって、ナッコプセを提供する韓国料理店が増えるのですが、2020年代に入ってすぐはコロナ禍の影響から、そのトレンドは必ずしも明瞭ではありませんでした。むしろ、コロナ禍がひと段落した2022年に台頭したチュクミのほうが、一世を風靡したのではないかと思います。
ナッコプセとチュクミはどちらも鉄板を使った炒め鍋ですが、ナッコプセがテナガダコを使うのに対し、チュクミはイイダコを用います。どちらも食感のよいタコであり、ピリッとした辛さが後を引くのも同じ。違いとして大きかったのは、シメのポックムパプ(チャーハン)にとびこを加え、ぷちぷちとした食感を活かしたのが特徴的だったのではないでしょうか。
個人的にはナッコプセがあったからこそ、ネクストとしてチュクミがうまくハマったと考えていたのですが、昨今の様子を見ていると、どうやらその流れもまた次なる下地になったようです。
■ 韓国からの進出店続々
今年2月に東京・新大久保で、韓国から進出してきたナッコプセの専門店「サウィ食堂」がオープンしました。2018年にソウル近郊の盆唐という新都市で創業し、短期間で30店舗以上を展開した伸び盛りのお店なのですが、社長さんの話によればチュクミのブームを見たことで、ナッコプセの可能性を感じたとのこと。




(右)フライドポテトを生地にしたようなチーズポテトチヂミ


(右)山手線の線路沿いに位置する新大久保本店
「日本の方はとてもタコがお好きですよね。サウィ食堂はソウルの聖水洞や孔徳などにもありますが、日本からも大勢の方がいらしています。」
他店との違いとして、コプチャンに変えてテッチャン(牛の大腸)を使用しているのが大きなポイント。より濃厚な脂の甘味が海鮮のダシと重なって深みのある味わいを生み出しています。4月には新大久保で2軒目もオープンし、7月には大阪にも進出を計画しているそうです。
なんと、大阪ですか。となるとよりいっそうブームの加熱が予想されますね。なにしろ大阪は大阪でナッコプセがたいへん盛り上がっているのです。
今年4月、難波千日前、鶴橋と立て続けにオープンしたのが「ケミチプ」。ナッコプセ好きのみなさんであれば、誰もが知るほどの超有名店です。釜山市中区の国際市場に本店を構える1972年創業の老舗店で、まさしく本場のナッコプセを携えて日本にやってきました。すでに大阪以外での出店もあり、関西方面からナッコプセの盛り上がりを牽引しています。
「コプチャンだけは輸入できないので日本のものを使っていますが、ほかはすべて韓国から持ってきています。厨房のスタッフも釜山で研修を積んできました。」
お店の方がアピールするのはやはり現地そのままの味。個人的には副菜として出てくるニラの和え物を、スタッフの方が釜山弁で「チョングジ(標準語ではプチュ)」と呼んでいたのが印象的でした。どんぶりのごはんにナッコプセを盛り、チョングジ、豆モヤシ、揉み海苔を加えてビビンバのように食べるのも現地流です。




(右)カリッと焼いた海鮮チヂミのほかケランチム(卵蒸し)も人気とか


(右)鶴橋駅前の焼肉通りに並ぶ鶴橋本店
韓国からの進出店が東京、関西で話題を集める状況を見るに、今後ナッコプセはより広範に知名度を獲得していくものと考えられます。
いくつか好材料と言えるのが、『孤独のグルメ』効果で一定の知名度があること、それをきっかけとしてメニューに加えた韓国料理店がすでに少なくないこと、チュクミのブームが下地になっていること、韓国内でもフランチャイズに勢いがあること、その影響が日本に波及してきていること、などがあげられるでしょうか。
ぜひともこの勢いでチーズタッカルビぐらい有名になって欲しいですね。ナッコプセの日本語訳は「テナガダコと牛ホルモンとエビの炒め鍋」のようにどうしても長くなるので、ナッコプセだけで通じるようになれば、ライターとしてはたいへん楽なのです。