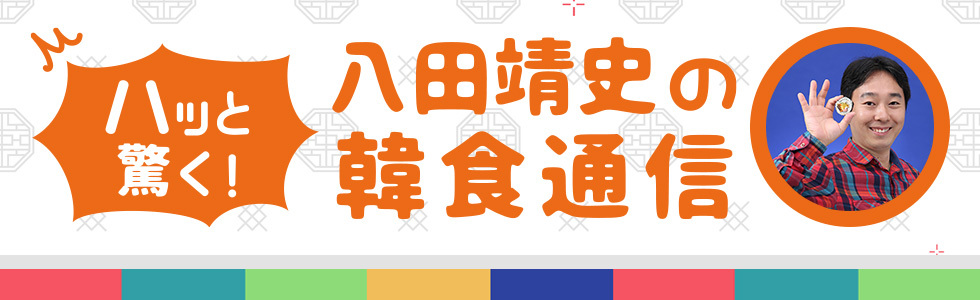日本の韓国グルメ事情を見るに、ここ1~2年で済州島の存在感がぐっと増してきたようです。朝鮮半島の南に浮かぶ韓国でもっとも大きな島。本土とは異なる独自の食文化を持つことに着目し、郷土料理を看板メニューに据える店や、済州島を店のコンセプトに掲げる店ができています。トレンドと呼ぶにはまだ少し気が早いかもしれませんが、少なくとも私の住む東京では、明らかにいい波が来ているように感じます。
しかもこれ、「次に来る」みたいな表現でなく、「ようやく来た!」「来るべくして来た!」現象ではないかなと。個人的な期待と妄想を交えながらの話になりますが、日本における済州島料理の近未来を鼻息荒く探ってみたいと思います。


(右)三姓穴。建国神話では穴から3人の神が生まれたとされる


(右)海女の石像。済州島では海女のとる魚介が名産となっている
と、その前に済州島の基本情報を少し。
済州島は韓国を代表する観光地のひとつで、中央部に標高1,947mの漢拏山が韓国最高峰(朝鮮半島北部を除く)としてそびえ、過去の噴火活動による独特の景観は、2007年に「済州火山島と溶岩洞窟群」としてユネスコの世界自然遺産に登録されました。自然景観を活かした見どころに恵まれ、かつては耽羅と呼ばれる独立国であったことから、島ならではの独特な文化が多く見られるのも特徴です。
食文化においても同様で、済州島ならではの料理が多数。
ハレの日に家族や親族、ご近所と分け合って食べる豚肉料理をはじめ、タチウオ、サバ、アマダイ、アワビ、ウニといった魚介類が豊富で、漢拏山があることから山菜、キノコ、高原野菜も自慢としています。南部を中心に柑橘類の栽培が盛んで、ミカンやデコポンは島を象徴する名産品。近年はリゾート地として、オシャレなカフェやベーカリーの集まるトレンドスポットとしての側面もありますね。
1度や2度行ったぐらいでは到底食べ切れないほど名物グルメの豊富な島。私も10回以上行きましたが、出合えていない宿題の料理がまだまだあります。

■ 地味だけど滋味深いスープ
それだけ豊富な郷土料理を抱える島ゆえに、2023年8月に東京・恵比寿でオープンした韓国料理店「SONON」が、「コサリユッケジャン(ワラビと豚肉のスープ)」を看板メニューに据えたと知ったときは、すごいチョイスをしたものだと驚きました。
ほかにいくらでも有名な郷土料理がある中で、失礼ながらだいぶ地味な一品。
ユッケジャンというと一般的には辛口の牛肉スープを想像しますが、済州島においてはコサリ(ワラビ)と豚肉をとろとろになるまで煮込み、そば粉でとろみをつけたスープを指します。辛さはほぼなく、ビジュアルはどろっとした茶色。昨今のSNS映えとは対極にあるような雰囲気ですが、食べてみると穏やかで、ホッと癒されるような滋味深さが持ち味です。現地では朝ごはんとして食べることも多いですね。


(右)明洞餃子。パスタマシンで手作りする皮は、極薄で具を包んだときに中が透けるほど


(右)店名の「SONON」はサンセットやサンライズ時のオレンジ色(鮮紅色)に由来
お店の方に尋ねたところ、
「韓国料理に自然派ワインを組み合わせるナチュラルさをコンセプトに、健康的でヘルシーな料理を探していたところ、イメージにぴったり合ったのがコサリユッケジャンでした。済州島ではなく京都のお店だったんですけど、事情を話したら快く教えてくださいまして、そのレシピをもとに独自の工夫も加えながら提供しています。」
とのことでした。
そこでピンときて確認したのですが、京都でコサリユッケジャンといえば河原町の「ハハハ」ですね。スンドゥブチゲ(辛口の豆腐鍋)などのスープ料理を得意とする「ピニョ食堂」や、釜山スタイルのホルモン焼きを提供する「ミリネヤンゴプチャン」など、独創的な韓国料理店を多数展開しているグループの1店です。なるほど、そこから広まっていったんですねぇ。
日本では馴染みの薄い料理だけに、オープン当初は不安もあったそうですが、実際に出してみると意外にもよく知っている人がいたり、同じく看板メニューの薄皮で包むふんわり食感の明洞餃子(明洞式の餃子)とも相性がよかったりと、女性客を中心にリピーターが増えて大成功だったそうです。


(右)「ハハハ」のコサリユッケジャン。済州島料理ブームの原点となるか?
■ タチウオ用の鍋が大活躍
次なる驚きは翌年。2024年7月に東京・新大久保でオープンした「OLLE」は、なんと済州島料理をメインのコンセプトに掲げました。店の入口には済州島の守り神「トルハルバン(石のおじいさん)」の石像が置かれ、店内もゴツゴツとした岩壁で覆われるなど、至るところで済州島らしさ満載です。店名は済州島の言葉で「家の前の路地道」を意味し、現在は島の各地を巡るトレッキングコースの名称としても使われていますが、これと標準語の「来る?(オルレ?)」を掛け合わせたそうです。


(右)「OLLE」の入口に鎮座するトルハルバン。階段を下りた地下に店がある


(右)チョプチャクピョクッ。骨付きの豚肉はハサミで切って味わう
メニューを見ても済州島料理がたくさんですが、中でも名産のタチウオを丸ごと調理できる超横長の鍋を用意しているのが目を引きました。済州島のタチウオ料理専門店で見かけるものですが、これを新大久保に持ってくるとは。しかも、済州島料理をコンセプトとしたからでなく、
「この鍋を活かしたくて済州島料理の店を始めることにしたんです。」
と順序が逆でした。
実際にメニューを見ると、横長鍋で「サムギョプサル(豚バラ肉の焼肉)」を焼いたり、「ナッコプセ(テナガダコと牛ホルモンとエビの炒め鍋)」を作ったりと、幅広い活用がなされていました。テーブルいっぱいに横臥するかのような鍋は迫力がありますし、みんなでつつきやすいとのメリットもありますね。
私はせっかくなので済州島料理にこだわって「カルチジョリム(タチウオの煮付け)」「コサリユッケジャン」「チョプチャクピョクッ(骨付き豚のスープ)」と注文してみましたが、次回は発展形のオリジナル鍋も試してみたいです。
■ 済州島の家庭料理を食べに
こうして済州島料理が身近になってくると、次に期待をかけたくなるのは昔ながらのコリアンタウンです。東京でいえば荒川区三河島、大阪でいえば鶴橋あたりには済州島出身の在日コリアンが多く、その歴史は100年以上にもなります。冒頭で「ようやく来た」「来るべくして来た」と書いたのにはそんな背景があり、そもそも日本には済州島をルーツとする方々が多く、済州島料理はもともと身近なのですよ。三河島や鶴橋で韓国料理店のメニューをよく見ると、ごく当たり前に済州島料理が混ざっています。


(右)荒川区役所の敷地内には済州市から贈られたトルハルバンがある
三河島の「オアシス」では、済州島出身のママさんが「モムクッ(ホンダワラのスープ)」や、「コサリコムタン(ワラビ入りの牛スープ)」といった料理を提供しています。モムクッは豚の背骨を煮込んだスープに海藻のホンダワラを入れたもの。コサリコムタンは牛のひざ軟骨を煮込んだスープにワラビを入れたもの。ホンダワラもワラビも、ママさんが地元で自ら仕入れてきたものだそうです。
さらには、「スジェビ(すいとん)」も済州島式だそうで、一般的には小麦粉で作るところを、そば粉100%で作っています。しかも、済州島産の生ワカメがたっぷり入っていて、
「済州島のオモニは子どもを産んだらこれを食べるんだよ!」
と教えてくれました。
産後の回復期に「ミヨックッ(ワカメスープ)」を食べるのはよく知られた話ですが、そば粉のスジェビを入れて作る話は初めて聞きました。コサリユッケジャンもそば粉でとろみをつけますが、そもそも済州島は稲作に不向きな土地柄なので、代替としてそばの利用が盛んなんですよね。そんな情報が頭の中でつながって、済州島への理解がいっそう深まった瞬間でした。


(右)モムクッ。済州島はかつて各家庭で豚を飼育していたため豚肉料理が豊富


(右)「オアシス」では韓国料理のほか、午前中はモーニングも提供する
今後、日本で済州島料理への注目度が高まるとして、わざわざ飛行機に乗らずとも身近にこうした本場があるとなれば、盛り上がりはより分厚くなっていくのではないでしょうか。個人的にはおおいに期待しています。
済州島料理は日本でこそもっと流行りませんか?